生物学を礎とした薬効・薬理研究からの新薬アプローチ探索と新薬の創製
薬効・薬理研究とは、薬が効く作用を評価する研究です。創薬研究(drug discovery)において、薬効・薬理研究機能は、新規物質創生(バイオ・化学)、薬物動態研究、安全性研究、創薬基盤技術開発と力を合わせ、画期的な新薬候補物質の創製に取り組んでいます。
創薬研究の過程で、薬が効く作用を評価することは「挑戦」です。なぜなら中外製薬が目指す新薬には、当社ならではの画期性が伴うからです。画期性は、世の中の先人や競合が踏み込んでいないところで生まれます。つまり、未踏の生物学的側面を見出し、それを科学的に評価できるよう実験系を構築・改良して精緻に適用する腕が肝要となります。
創薬研究は、新薬として魅力的な新薬アプローチを考案・探索することから始まります。これには研究本部全体が関与しますが、薬効・薬理研究機能はその中心的役割を担います。当社内を源泉とするだけでなく、大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFReC)など国内外の研究機関とのコラボレーションも源泉として、次元の違う生活の質を患者さん・ご家族に届けることを目指し、当社ならでは新薬アプローチを編み出します。その過程において、考案・探索した新薬アプローチの妥当性につき実験的な初期検討も行います。
次いで、新薬候補物質の同定に向け新規物質創生機能が動き始めると、薬効・薬理研究機能では、先に述べたように実験系(in vitro / in vivo薬効評価系)の構築/改良を行うとともに、それら評価系を用いて創製した物質群の評価を行います。そうして試行錯誤を繰り返し、各機能とともに新薬候補物質の素となる「リード物質」を創製します。
その後はリード物質の最適化段階に進み、新薬候補物質を同定します。薬効・薬理研究機能は、リード物質を改変した物質群につき、さらなる薬効評価・作用機序解析を実施し、加えてバイオマーカー探索も行い、新薬候補物質同定過程の中で欠かせない役割を果たします。
新薬候補物質が臨床開発ステージに進んだ後も、薬効・薬理研究機能では非臨床薬効・薬理データを積み重ね、新薬として承認を得るために貢献します。
Researcher's Voice
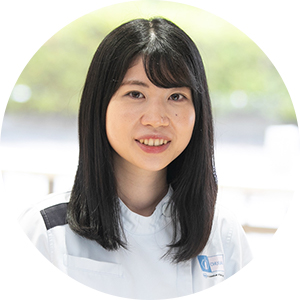
畑野 阿希Hatano-Aki
薬学系研究科 薬科学専攻 修了
2018年入社
やりがいのある薬効メカニズムの検証。
毎回答え合わせのような楽しさがあります
現在の仕事・自身の役割は?
創薬プロジェクトを推進するための薬効評価を行っています。また、そこで必要とされる実験系や、作用機構を確認するための評価系の構築に力を注いでいます。さらにこれと並行して、新しい創薬プロジェクトについて考案することも行っています。
具体的にどのような研究を?
合成された化合物を細胞や動物に試し、どの程度の効果があるのかを評価しています。評価においては、目的にかなう最適な評価系の確立が不可欠です。いかなる系にすれば知りたい情報が得られるのか、また、安定した結果を得るためにはどのような工夫の余地があるかなど、さまざまな検討を重ねながら評価系を確立しています。
やりがいやおもしろさは?
自分たちが想定したメカニズムが正しいのか否かを検証するところに、大きなやりがいを感じています。検証方法を考え、実行し、結果が出た際には、事前の想定と実際の機序が合っていたかどうかを確認します。想定と違っていた場合は、方法も含めてどこかに間違いがあるのかを探索し、再度検証を行います。こうした作業には、毎回答え合わせのような楽しさがあります。
職場環境の特徴や魅力は?
頭の回転が早く理解力が高い人に囲まれ、情報や考えの共有がとてもスムーズに行える点に魅力を感じています。また、生物という分野に限らず、「考える」ということの本質を教えてもらえる職場であり、知的欲求を高いレベルで満たしてくれる環境にいると感じています。
将来の目標は?
あらゆる物事に対して、理解できる範囲を広げていきたいと考えています。
主な研究テーマ
- 新薬アプローチの探索
- in vitro/in vivo薬効評価
- 薬剤作用機序解析
- バイオマーカー探索
基盤となる技術
- FACS(fluorescence activated cell sorting)
ヒト、動物の細胞を多分画に分け、遺伝子発現の特徴などを明らかにする。標的分子探索、薬効の定量化、機序解明などに活用する。 - 目的遺伝子発現制御技術
培養細胞から動物まで、目的遺伝子の発現ON/OFFなどによる標的分子/新薬アプローチの妥当性検討、薬剤作用機序解析など様々な目的で活用する。 - in vivo薬効評価
創製した物質がどの程度薬効を示しうるかどうかを見積もるため、動物愛護に十分配慮しながら、動物モデルで評価すること。それぞれの新薬アプローチが狙っているヒト病態の生物学的側面を切り出して、それを反映するような動物モデルを構築し、活用する。
研究機器・設備・施設
- FACS(fluorescence activated cell sorting)

単一細胞あたり30種類以上の分子を同時に測定することができる、最先端のフローサイトメーター。多様な細胞群の複雑な特徴を一度に測定できるため、希少な臨床検体の解析に使用されており、標的分子/新薬アプローチやバイオマーカーの探索、疾患メカニズムの解明に活用されている。