臨床を通じて得られた製品情報から、より適切な治療法を探索する
薬は治験を経て製品となってからも、その薬に関する調査や研究・臨床試験が行われ、得られた情報が新しい治療法や副作用の軽減、より良い使用法などに役立てられます。このプロセスを「育薬」といいます。創薬は新薬を世に出すことで、育薬はより適した治療をエビデンスに基づいて提案することで、未だ充足されていない医療ニーズの解消に寄与し患者さんの利益に貢献しています。育薬研究はプロダクトリサーチ部が担当しており、開発後期段階以降の薬剤を対象とした非臨床研究を行っています。
育薬研究の大きな特徴は、実際に臨床で投与された患者さんがいらっしゃる薬剤を研究の対象としていることです。私たちは臨床を通じて収集された情報やそこから生み出される仮説を基礎研究などによって科学的に証明し、より適切な患者さんの治療に、より納得性高くつなげていくことを目指しています。具体的には、薬剤の作用機序や耐性機序の解明、他の薬と併用した場合の有用性の検証などの非臨床エビデンス創出と提示、有効性や安全性を予測し得るバイオマーカーの探索、および薬の安全性に関わる情報の創出と提供などが挙げられます。社内外の専門家・医療関係者とのコミュニケーションや、より臨床を反映した病態モデルの確立、薬剤の機序解明・薬効研究による実臨床への情報提供は、育薬研究ならではの醍醐味です。さらにはこれらを通じて新薬創製の糸口を見出し、新たな創薬研究につなげていくことも役割の一つと考えています。
こうした特徴から、プロダクトリサーチ部の活動する場は実験室にとどまらず医療現場にもあるといえます。また製品のライフサイクル戦略や安全性面への対応から、社内ではメディカルアフェアーズ本部内の連携のみならず、プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット、研究本部、臨床開発本部、TR本部、医薬安全性本部、信頼性保証部門などの各部門、またアライアンスを結んでいるロシュ社やジェネンテック社との連携も不可欠となっています。私たちプロダクトリサーチ部は、患者さんを大切にする会社の理念を実現する中外独自の研究機能組織といえます。
Researcher's Voice
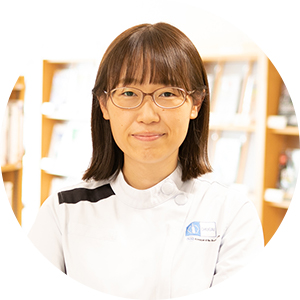
森永 真実子Morinaga-Mamiko
農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 修了
2019年入社
今ある薬で、今いる患者さんのために。
個別化医療や新しい臨床試験に貢献したい
現在の仕事・自身の役割は?
育薬研究は、今ある薬についての研究を行い、製品化後に実際の医療現場で必要になるエビデンスを創出することで、文字通り薬を育てる研究です。他薬剤との併用治療効果の検討や、副作用の低減、薬剤耐性後の治療提案、治療効果を予測するバイオマーカーの提案、適応拡大など、製品化後の研究によって薬の有用性をさらに高めるための研究をしています。その中で、私は主にがん免疫に関する非臨床研究を行っています。
具体的にどのような研究を?
開発中の薬剤に関する非臨床育薬研究に携わっています。この薬剤は臨床開発の後期段階にあり、患者さんに対する安全性と有効性の評価が行われています。細胞や動物モデルを用いた非臨床研究では、治験に参加されている患者さんの検体だけでは実施できないような、さまざまな解析を行うことができます。「この薬がなぜ、どのように効くのか?」をより詳細に明らかにすることで、どのような患者さんに有効なのか考察し、個別化医療や、新しい臨床試験の実施へ貢献できればと考えています。
やりがいやおもしろさは?
創薬研究では実際に薬が患者さんに届くまでに長い時間がかかりますが(もちろん、未来のたくさんの患者さんに役立つのですが!)、育薬研究は今ある薬で、今いる患者さんに貢献できるという点に、魅力を感じています。研究のスタートから、どのようなエビデンスがあると患者さんの幸せにつながるかを考え、研究を実施してエビデンスを創出し、医療現場へ届ける。この一連のプロセスに携われることに、大きなやりがいを感じます。
職場環境の特徴や魅力は?
さまざまな専門性を持った人が部内・研究所内に集まっていて、しかも皆とても親切で研究好きです。面白いデータが出たら、近くに座っている人にすぐ報告できるような雰囲気があり、考察や次の計画を議論しているときはとてもワクワクします。また「こんなことできるかな?」といったちょっとした思いつきも、詳しそうな人に相談に行くと熱心に議論してくれて、具現化までの道筋が見えてきます。
将来の目標は?
まだまだ道は遠く、それがどのようなものなのか輪郭もまだ見えていませんが、患者さんに希望を持ってもらえるような研究を実現したいです。
育薬研究の担当グループ構成と担当業務
- 育薬研究推進グループ
- 育薬研究実施におけるコンプライアンスの維持・向上や外部研究機関との共同研究の推進。病理解析や測定といった領域横断的な研究や安全性に関わる試験も担当。
- オンコロジー育薬研究 1G
- がん患者さんに有用な情報を創出するための後期開発品・製品研究を実施(主に分子標的薬):薬剤の作用機序・耐性機序解明、併用療法の有用性評価、新規治療提案、バイオマーカー探索など
- オンコロジー育薬研究 2G
- がん患者さんに有用な情報を創出するための後期開発品・製品研究を実施(主にがん免疫薬):薬剤の作用機序・耐性機序解明、併用療法の有用性評価、新規治療提案、バイオマーカー探索など
- スペシャリティ育薬研究 1G
- 血液・眼科領域疾患患者さんに有用な情報を創出するための後期開発品・製品研究を実施:作用機序解明、適応拡大、新規治療提案、バイオマーカー探索など
- スペシャリティ育薬研究 2G
- 自己免疫疾患、神経疾患患者さんに有用な情報を創出するための後期開発品・製品研究を実施:作用機序解明、適応拡大、新規治療提案、バイオマーカー探索など
主な研究テーマ
- 免疫チェックポイント阻害剤を中心としたがん免疫治療薬の作用機序、耐性機序、他剤との併用効果の探索
- ALK融合遺伝子陽性肺がんにおけるアレクチニブの耐性機序解析と新規治療法の探索
- リンパ腫治療薬の作用機序、耐性機序や他剤との併用効果の探索
- エミシズマブの適正使用に向けたエビデンス創出や、適応拡大、血友病患者さんの疾患モニタリング法の探索
- 網膜関連疾患の病態メカニズム解明と薬剤の作用機序、およびバイオマーカー探索
- 自己免疫疾患、神経疾患の病態メカニズム解明と薬剤の作用機序の探索、およびバイオマーカー探索
戦略領域ごとの主な担当製品
- がん領域
アレクチニブ、アテゾリズマブ、ベバシズマブ、オビヌツズマブ、ポラツズマブベドチン - スペシャリティ領域
トシリズマブ、サトラリズマブ、エミシズマブ、ファリシマブ
研究機器・設備・施設
- MRI System 7T/210

MRI System 7T/210は小動物用の高磁場MRIとしてトップレベルの性能を有するin vivo画像装置である。高い空間分解能の撮像に優れ、病変の経時的変化を非侵襲的に解析できる。MRIは臨床現場で画像診断として急速に進歩・浸透しており、基礎研究での応用価値は非常に高い。現在、がん研究や各種病態モデルの様々な解析を実施している。