革新的分析技術とデジタル技術を活用した医薬品の品質設計で、世界中の患者さんに寄り添った新薬開発をリードする
開発候補化合物を選択する段階から、薬制当局(日・米・欧など)に新薬の承認申請を行い、製品の製造を可能とする段階までの期間を担当します。製品を開発するうえで医薬品の特性を深く理解し、医薬品の有効性・安全性につながる品質を、数多くの分析データを基に設計するのが分析技術研究の役割です。バイオ(抗体などのタンパク質など)とケミカル(低・中分子化合物)間で、適用する分析技術や評価項目に多少の違いはありますが、基本的な考えは同じです。
まずは原薬の構造確認と、基本的な物性を調べることから始めます。例えば温度に対してどのくらい安定なのか、どのような構造上の変化や分解物ができるのかなど、さまざまな分析技術やアイデアを駆使して、構造や特性を明らかにします。
バイオ分野ではリサイクリング抗体やバイスペシフィック抗体ならではの分子機能や構造を解析し、ケミカル分野では低分子医薬品に加え、構造や物性がユニークな中分子医薬品の結晶構造解析や、製剤化した際の機能解析を行います。また、最新の分析技術を用いて、ごく微量の不純物についての特性を解析するなど、医薬品の品質を多面的に理解することを目指しています。これらの研究を通じて、有益な薬を患者さんに一日も早くお届けすることが、分析技術研究の目標です。
最近では、デジタル技術の活用が重要な役割を果たしており、ロボットによる自動分析装置(Laboratory Automation System)や、IT技術を用いた試験や文書管理業務の効率化・標準化に取り組んでいます。さらに、データサイエンスを活用した機械学習・AI技術やモデリング&シミュレーション技術を駆使して、開発加速やコスト競争力の高いプロセス構築を推進しています。また、世界的な医薬品開発では、ロシュ社をはじめ海外他社との協働の機会も多く、日々英語によるコミュニケーションなどグローバルな連携も図っています。
Researcher's Voice
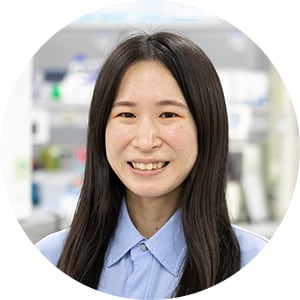
嶋田 麻里Shimada-Mari
工学研究科 生物工学専攻 修了
2018年入社
バイオ医薬品の品質管理のための試験法を開発。
分析研究の存在感を社内外に示したい
現在の仕事・自身の役割は?
質量分析計を用いた一次構造分析法の試験法開発や、抗体の確認試験に用いられる試験法を開発し、GMP(※)担当部門に試験法の技術移管を行っています。また、質量分析法チームのリーダーとして、試験法の開発状況や日々の中で生じるトラブルについて、分析研究部側、GMP側の課題にかかわらず試験法チームの会議体で共有し、議論の場としています。
- GMP(Good Manufacturing Practice:医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準)
具体的にどのような研究を?
バイオ医薬品特有の唯一無二のアミノ酸配列が、設計された配列通りに構成されているかどうか、また、製造過程の中でさまざまなストレスにさらされる抗体が、どれほどの化学修飾を受けるのかを質量分析計でアミノ酸レベルで解析し、抗体が持つ性質をデータで示していきます。また、品質管理の手法となる試験法が開発された際は、GMP担当部門への技術移管対応も実施しています。
やりがいやおもしろさは?
医薬品は上市されるまでに長い年月がかかりますが、その中で、この抗体は現在どのような段階にあり、いかなる試験法が求められているのかや、それぞれの抗体が抱える課題を知り、それに取り組んでいけることです。各々が独自の専門性や、さまざまなアイデアを持ち寄り、解決へとつなげていけることはこの研究の醍醐味です。治験で自分の関わる医薬品が患者さんに投与され、効果を発揮していることを聞くと、微力ながら力になれていることを感じ、それがやりがいに繋がっています。
職場環境の特徴や魅力は?
明るくオープンな性格の方が多く、とてもにぎやかな職場です。若手から経験豊富なベテランの方まで在籍し、何か議論したいことや実験でうまくいかないことなどがあれば、気軽に相談に乗ってもらえます。自分には考えもつかないような意見が返ってくることも往々にしてあります。上司や同僚ともフランクに相談し合い、語り合える風土が根づき、日々居室や実験室のどこかで自由闊達な議論が行われている環境です。
将来の目標は?
中外製薬はこれまで、国内のバイオ医薬品分野でトップを走ってきました。しかし、近年は抗体医薬品はますます機能が複雑化し、開発のスピードアップが求められ、分析への難易度は上がってきています。そんな状況の中でも、中外製薬の分析研究の存在感を社内外にアピールしていけるよう、自身の専門性をさらに高め、データに謙虚で素直に取り組み、より多くの患者さんに貢献していきたいと思います。
主な研究テーマ
- バイオ医薬品、低・中分子医薬品の構造解析及び分子機能解析
- 高濃度抗体医薬製剤と会合化メカニズムの解明
- 不純物・分解物の微量構造解析
- 統合的自動化とデータマネジメントシステムの展開
- 製造工程由来不純物(HCP等)のIdentificationとリスク評価
- 原薬・製剤の固体状態での物性評価
- デジタル技術の製薬・生産課題解決への適用
基盤となる技術
- 構造解析技術
原薬のみならず不純物や分解物の構造を解明し、医薬品の有効性・安全性の観点から品質を調べる。バイオロジクスではLC/MS、低分子化合物ではNMRなどの機器分析が有力な手段となっている。 - 国際レギュラトリーサイエンス
国際的に調和されたガイドラインの内容とその科学的背景に加え、最新技術動向や各国の薬事的要求事項に対応する。各国当局からの査察を受けることもあり、世界各国に対応した開発研究体制の構築が必要となっている。 - QbD(Quality by Design)
製品品質と製造工程の関連性を把握、それらを管理することで、デザインした品質の医薬品を再現よく製造することが可能となる。各医薬品の重要品質特性を見極め、製造部門と品質部門が一緒に「品質を作り込む」ために、各種実験にも実験計画法や品質工学を盛り込むことを進めている。
研究機器・設備・施設
- リキッドハンドリングプラットフォーム(Freedom Evo®)

目的蛋白質の精製を自動化する装置。バイオ原薬の製法開発のための細胞株選抜および培養工程/精製工程のプロセス評価の迅速化が可能。
- 2次元液体クロマトグラフィー(2D-LC)

異なる分離条件を組み合わせて2段階での分離分析を行う装置。