バイオ技術との融合により、限界を超える化学創薬に挑む
ケミカル医薬品は化学で製造される医薬品です。一般的には「化学を基盤とした創薬が限界に近づいた」と言われていますが、私たちは新たに中分子の可能性に注目し、化学創薬の新たな領域の開拓を追求しています。当社の中分子技術は、「バイオと化学の融合」から生まれました。2つしかないモノづくり技術であるバイオと化学が切磋琢磨することで、従来には不可能であった創薬が可能となり得ます。
低分子創薬では、ロシュ・グループとして保有する基盤技術を駆使して、常識を変えるような新薬を創出するにとどまらず、新たな切り口と技術の深化から、これまでにない創薬を目指しています。その一例が、薬のタネになる化合物を発見(ヒット創出)する新手法開発の試みです。これは、この30年間、創薬化学の活動範囲が、化合物最適化に限定され続けてきたことと対照的です。
化学を基盤とした創薬においても、新しい手法を生み出す多様な能力が重要となると考えています。より複雑な構造を有する化合物を自由自在に操れる能力、目的の化学反応だけを選択的に行う技術を開発する能力、複雑な生体系を反映させてシミュレーションする計算能力、見えなかったものを見えるようにする分析化学的な能力などです。
私たちの強みの1つは、世界で最も優れたバイオ研究者集団の活動を間近に見られることです。技術を深化させ、従来不可能であった創薬を実現させていく研究姿勢が、現在のバイオ医薬の隆盛をもたらしました。化学創薬でも同様の取り組みが「限界」の打破を可能にするはずです。
ケミカル医薬品にしかできない創薬を、最先端の技術を駆使し、さまざまな分野の方たちと切磋琢磨し、融合することによって実現していく。そうした気概のある、高い専門性を有する方の入社を心待ちにしています。
Researcher's Voice
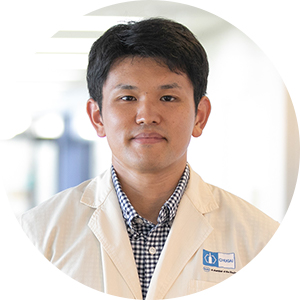
畠中 渉Hatanaka-Wataru
工学府 材料物性工学 専攻
2019年入社
中分子創薬の初期段階のテーマを研究。
恐れず挑戦を促してくれる風土がある
現在の仕事・自身の役割は?
中分子(ペプチド)の合成と合成に関連したさまざまな業務に携わっています。また、入社1年目に提案した中分子とは異なるモダリティに関するテーマについても、並行して業務を行っています。
具体的にどのような研究を?
ペプチドに関連した業務では、創薬の初期段階のテーマを担当しています。実務としては、ペプチドの設計や合成が中心です。また、ペプチドの合成に必要なアミノ酸の在庫管理やCROとのやり取りなど、実験業務以外についても担当しています。中分子とは異なるモダリティに関しては、より早期の技術検証を中心に必要な分子の合成とvitro評価を行っています。こちらはペプチドのテーマ以上に社内の化学部以外の方との議論が多く、テーマの進め方など非常に多くの学びがあります。
やりがいやおもしろさは?
どちらのテーマも技術検証を含んだ早期の内容なので、「仮説を立て検証する」の繰り返しの中で、これまで未解明であったことがわかってくる過程にはワクワクします。そして、この過程の先には、まだ治療法のない病に悩む患者さんに有効な薬が創れる可能性があります。この点で、自身の仕事に日々意義を感じられ、検証がうまくいかないときも励みになっています。
職場環境の特徴や魅力は?
恐れず挑戦することを促す雰囲気があると感じます。失敗も次への学びにできるようなアドバイスをもらえる場面が多く、結果的に若手含め多くの人が「挑戦してみよう」と思える環境です。また、人格的にも優れた人が多く、助けてもらったぶん自分も他の人の役に立とうと自然に思うことができる環境は魅力です。学生時代は「やりたい研究ができる環境があればいい」と考えていましたが、人と関わらずに研究を進めることは不可能です。素晴らしい人たちに囲まれて研究ができることも、とても重要なのだと感じる毎日です。
将来の目標は?
「健康が当たり前の社会や生活」を実現できるよう、研究者として微力ながら貢献していきたいと考えています。未だ有効な治療法のない疾患に対する薬を創ることは、この目標を実現する一つの手段となります。そして、その目標を達成することができれば、私にとっても良い人生になるでしょう。そうした思いで日々研究に取り組んでいます。
主な研究テーマ
- ヒット創出(Hit generation)
- 化合物最適化(Lead optimization)
- 初期プロセス研究
基盤となる技術
- 中分子化合物創製技術
一般に低分子では困難とされる細胞内タンパク質間相互作用の阻害を実現できる、これまでにない医薬品の創製が可能となる。これまでにない医薬品を目指し研究を進めており、合成化学だけでなく、薬物動態を含めた広範な知識を必要とする。 - 低分子化合物創製技術(ロシュ・グループ内相互情報共有)
約300万種類あるロシュ・グループの化合物を用いたHigh throughput screening (HTS)を実施することができる。ロシュ社との技術交流により、世界トップクラスの優れた創薬化学技術を保有しており、多様な標的分子に対して薬のタネとなる化合物を創出すること(ヒット創出)が可能となる。さらに、全化合物情報を集約したデータベースを共有し、アッセイデータに研究員はいつでもアクセスできる。 - 合成化学技術
合成化学が活躍できる場面は多岐にわたる。薬のタネを見出すヒット創出、ヒット化合物を薬として仕上げてゆく化合物最適化、そして化合物をヒトに投与できるように仕上げていくプロセス研究である。いずれも、深い合成化学に対する洞察が必要となる。 - 計算科学技術・データサイエンス
薬の分子構造を適切に決定していくため、あるいは薬のタネの創出の両方に重要な技術。最先端の計算科学・データサイエンスを用いれば、人間には想像できないような合理的な答えを導いてくれる場面もある。薬効を増強させるためだけでなく、安全性を得る目的など多方面からの活動がある。